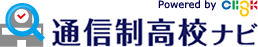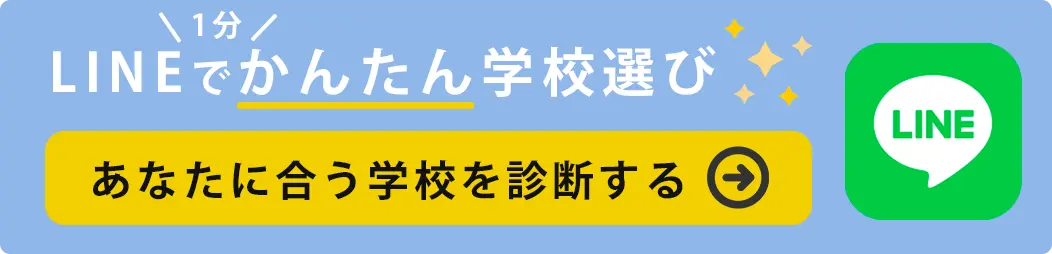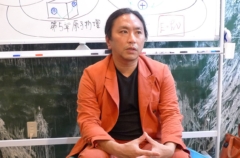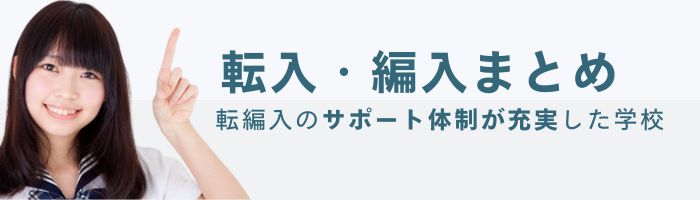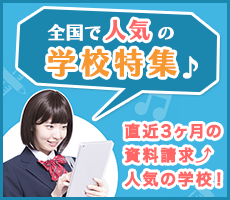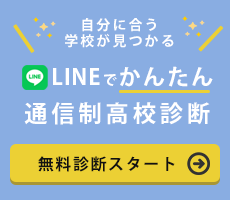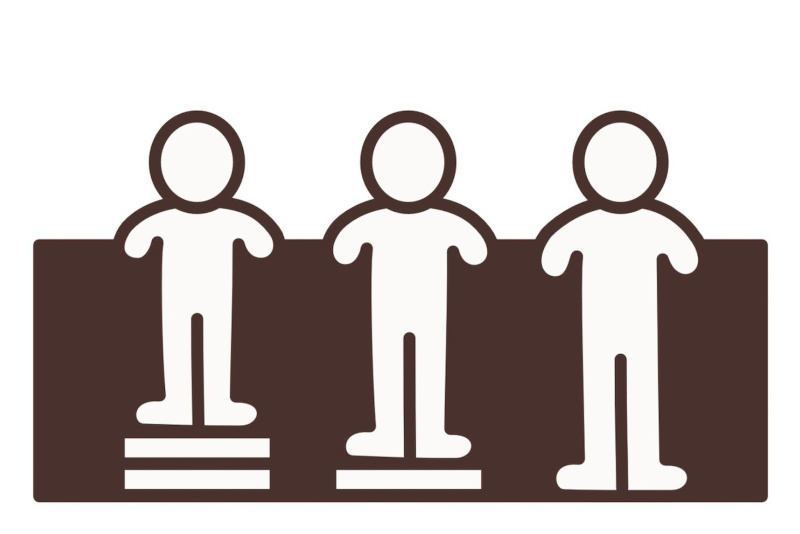
「うちの子、授業についていけているのかな…?」
そんな不安を抱く保護者は少なくありません。実際に、教室の中には発達障害や学習障害といった「合理的配慮」が必要な子どもが一定数いることが分かっています。
こうした子どもたちの教育を受ける権利を保障するため、2016年に公立学校で「合理的配慮」が義務化され、2024年には私立を含むすべての学校にも拡大されました。合理的配慮とは、障害や特性、状況に応じて学校が個別に環境を工夫し、学習を支える取り組みのことです。
たとえば視覚障害がある子どもには、文字の大きい教科書や音声読み上げソフトを用意したり、教室の前方に席を配置するなどの工夫がなされます。聴覚障害や肢体不自由、知的障害など、障害の種類に応じて環境を整えることは当然のことながら、発達障害の子どもに対しても同様に義務づけられています。
けれども現場には、教員の理解不足や過重な負担といった課題が立ちはだかっています。発達障害の特性は一人ひとり違うため、決まったマニュアルで支援できるわけではなく、学校ごとに試行錯誤を繰り返しているのが実情です。
では現実には、発達障害の子どもたちへの合理的配慮はどの程度進んでいるのでしょうか。そして、学校現場ではどのような工夫や取り組みがなされているのでしょうか。
本記事では、学習障害への支援事業を展開する「一般社団法人読み書き配慮」代表の菊田史子さんに、その実情を伺いました。
合理的配慮は実際どこまで進んでいる?
—— 学校において合理的配慮が義務化されて以降、実際に、環境整備は進んでいるのでしょうか。
菊田さん:先に義務化されている公立の学校ではかなり進んでいます。ただ、学校や地域によって取り組みの進み具合はまちまちで、その地域の教育委員会や学校の管理職の意識によっても違いが出ています。私は2015年から東京都新宿区で教育委員を務めましたが、新宿区の教育委員会は新しいことにチャレンジしやすい環境で、発達障害の生徒たちへの合理的配慮も早くから進んでいたように感じます。
—— そもそも、発達障害によって学習に困難を抱えている生徒がいることについては、理解が進んでいるのでしょうか。
菊田さん:教員の研修会では発達障害の生徒への理解や授業での工夫のしかたを学べるので、まったく知識がないという教員はいないはずです。中でもADHD(注意欠如・多動性障害)やASD(自閉スペクトラム症)については理解が深まってきています。一方で、読み書きや計算に困難を抱えるLD(学習障害)については、まだこれからという段階です。
—— 文部科学省による2022年の調査では、通常の学級の中で特別な教育的支援を必要とする児童・生徒は、小・中学校で8.8%に上るという結果が出ています(「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」より)。30〜40人の学級なら2〜3人が該当する計算になりますから、そうした子どもたちが取りこぼされることなく教育を受けられる環境づくりは必要ですね。
菊田さん:同調査の2012年の結果では、小・中学校で6.5%という数字が出ていました。10年で数値が2.3%上がっている背景のひとつには、教員による特別支援教育に関する理解が進んだことが挙げられると思います。熱心な教員が理解を深めてさまざまな工夫を取り入れていくことで、それが学校全体に広がっていったり、その教員が転勤して別の学校でも積極的に取り組むようになったりして、合理的配慮の実践が広がっている状況ですね。
—— 合理的配慮が義務化されたといっても、「こう診断された生徒がいたらこうしなさい」という統一のルールがあるわけではないので、教員の考え方や積極性次第で取り組みには濃淡が出るわけですね。
菊田さん:発達障害とひと言で言っても、何にどの程度困難を抱えているかは一人ひとり違うので、一律に配慮の方法を決められるわけではありません。制度で一律に決めるのではなく個別に向き合うことが必要になるため、濃淡はどうしても出てしまいます。
パソコンやタブレットの活用も進む
—— では、現在学校で取り入れられている合理的配慮の実践例を教えてください。
菊田さん:たとえば、文字を書くことに困難のある生徒に対して、ペンとノートを使う代わりにタブレットやパソコンを活用する事例は増えています。テストではひらがなでの解答でも正解にしたり、テストをパソコンで受けられるようにしたりするケースもあります。文字を読むことに困難のある生徒には、パソコンやタブレットで文字を読み上げるソフトを使う事例もあります。大学入試でも、音声読み上げや試験時間の延長、別室での受験などの配慮が提供されるようになっています。
—— IT化が進んだことで、環境を整えやすくなってきているのですね。
菊田さん:はい。特にLDの子どもには、ITを使うことで学習がスムーズになるケースが多く見られます。ただ、道具を変えればすぐに学習ができるようになるわけでなく、道具が合わなかった間の学習の遅れを取り戻すことも必要になります。その遅れを埋めるにも、代筆・代読をしてくれる学習アプリなどが役立っています。
—— さまざまなツールがある中で、生徒に合ったものを見つけていくことが大切ですね。
菊田さん:GIGAスクール構想による一人一台端末の導入によって、合理的配慮の幅も広がっています。ただ、学校によってはITに関する知識が遅れていて、学校指定のタブレットやパソコンでなければ使えず、読み上げソフトが使えなかったり、スムーズに学習するには向いていない端末だったりすることもあります。iOS端末のほうが圧倒的に使いやすいのに許可されないといったケースも聞きます。一般社会と比べて学校ではIT化が大きく遅れているのが現状で、その遅れが合理的配慮にも関わってきているんです。
—— ITの活用以外では、どのような工夫があるのでしょうか。
菊田さん:黒板の周りの掲示物を最低限にして視覚的な刺激を減らすことや、机や椅子の脚にテニスボールをつけて聴覚的な刺激を減らすといった工夫などが広まっています。
—— 学校ではどのようなプロセスで、合理的配慮が実践されていくのでしょうか。
菊田さん:生徒によってニーズはそれぞれ違うので、何につまずいていて、どうしたら学びやすくなるかに目を向けながら、実践していく形になります。特別支援教育については校長が特別支援教育コーディネーターを指名し、また校内委員会を組織します。校内委員会では障害のある児童・生徒への支援体制について話し合い、個々のニーズに基づいて対応を決めていきます。特別支援教育コーディネーターは学校内の関係者や外部機関との連絡調整、保護者の相談窓口などを担うことになります。
—— 特別支援教育コーディネーターとなった人の実力によっても、取り組みに差が出てくるのでしょうか。
菊田さん:実際には学習障害やITにあまり詳しくない教員が指名されてしまうケースもあるので、差が出てしまうこともあると思います。また、特別支援コーディネーターの職務を任されても、必ずしも手当が出るわけではないので、そこは改善が必要だと思います。
—— 社会問題化している教員の労働環境については、合理的配慮を進めるためにも解決が必要ですね。

自身で合理的配慮を申請できる力も必要
—— 発達障害などで合理的配慮が必要だと感じる児童・生徒は、学校にどのように対応を進めてもらえばいいのでしょうか。
菊田さん:合理的配慮は、基本的には本人や家庭からの相談や申請から始まります。学校に何も相談しなくても教員が気付いて動いてくれることもありますが、まずは本人側からニーズを伝えることが重要です。「勉強が遅れているので何とかしてください」と漠然と伝えるのではなく、「ノートをとるのが困難なので、パソコンを使わせてほしい」など、具体的に伝えていくと、学校も動きやすくなります。また、パソコンを使いたいのであればキーボードのタイピングなどの操作はできるように練習しておくなどの準備は必要です。
—— すべてを学校任せにするのではなく、本人が自分の特性を理解して、対応策を考えていくことも必要なんですね。
菊田さん:はい。ある高校で発達障害について講演をしたときに、多くの生徒たちから「もっと早く知りたかった」「私はこれだったんだ」という感想をもらったことがあったんです。発達障害についての知識がなく、周囲の大人も誰も教えてくれなかったので、勉強ができない自分はダメな人間だと思っていた、と言うんですね。保護者が発達障害をネガティブにとらえているために、「特性に応じて工夫していこう」という話が親子の中で出てこず、自己肯定感が低くなってしまっている生徒もたくさんいるんです。
—— 特性と向き合うことができずにいると、学校に対応を依頼することもできないし、自己肯定感を上げることも難しくなっていくわけですね。
菊田さん:社会に出たときにも、自分の特性がわかっていれば働きやすくなりますし、自己否定的になって精神的に不安定になるなどの二次障害も防ぐことができます。学校でも、合理的配慮を進めていく中で、「生徒の配慮申請のスキルを上げる」ことも意識してほしいと思います。自分のことをうまく理解して説明できるスキル、相手に理解してもらうスキルは将来的に欠かせません。「あきらめずに、自分で申請してみよう」と指導してもらえるとよいですね。
—— 合理的配慮を実践するかしないかという段階ではなく、実践したうえで、子どもたちが学校を卒業した後の生きづらさを軽減させていくことに目を向けてもらえたらベストですね。
菊田さん:そのとおりです。発達障害は、その特性から大きく成功する人も多くいます。世界的に有名な成功者たちの大半が発達障害の傾向があるとも言われています。その特性を活かせるように、今ある困難を軽減する工夫をしながら、ポジティブに学んでいってほしいと思います。
—— ありがとうございました。
取材協力

菊田史子さん
「一般社団法人読み書き配慮」代表理事。元新宿区教育委員。 長男は読み書きに困難を抱える学習障害を持ち、合理的配慮を得て慶応義塾大学へ進学。こうした経験から2018年に「一般社団法人読み書き配慮」を立ち上げ、学習障害の子どもへの合理的配慮のデータベースを軸に、学習障害の理解、検査、支援に関わる事業を展開する。その一つに「読み書き苦手な子供のスクールKI・KU・TA」がある。
<取材・文/大西桃子>
この記事を書いたのは

ライター、編集者。出版社3社の勤務を経て2012年フリーに。月刊誌、夕刊紙、単行本などの編集・執筆を行う。本業の傍ら、低所得世帯の中学生を対象にした無料塾を2014年より運営。