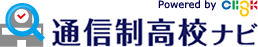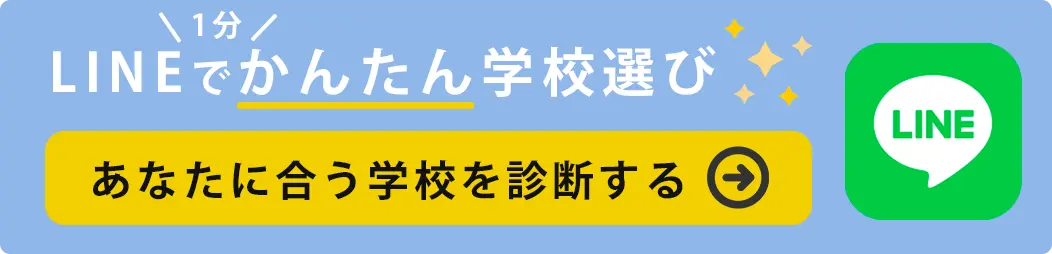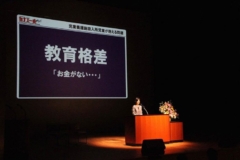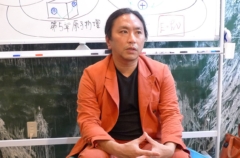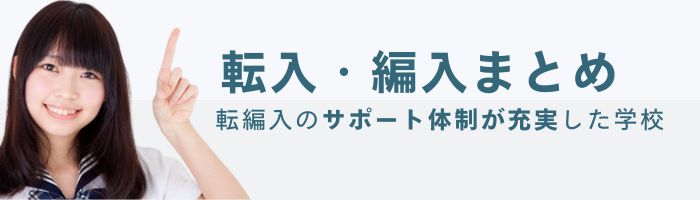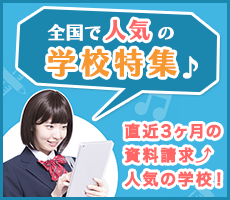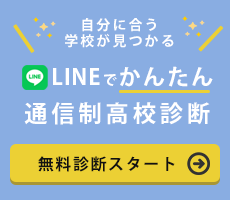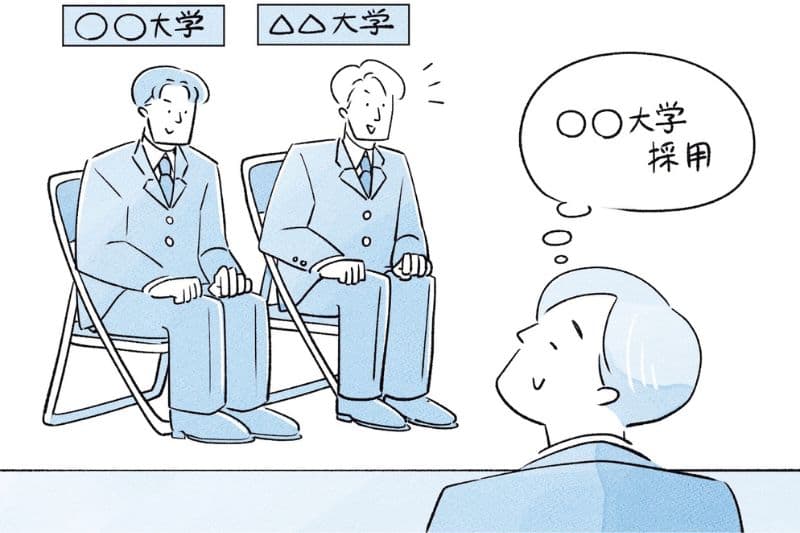
子どもの進路に悩む保護者の中には、「通信制高校を選んで本当に大丈夫?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
不登校や発達障害を抱えている、あるいは好きなことを学びたいという理由で通信制高校を進学の選択肢に入れる生徒は増えています。しかし一方で、まだ「学歴社会」の風潮も残る中で、通信制高校を選ぶことに不安を感じる人も少なくありません。
世間では、「安定した収入を得るためには学歴は重要」という声もあれば、「社会に出てしまえば学歴は関係ない」と反論する人もいて、常に論戦が繰り広げられているのが現状です。では実際、これからの社会で学歴はどのようにとらえていけばいいのでしょうか? そして、学歴に不安を感じている中・高生たちは、今何をすればいいのでしょうか?
今回は、2025年3月に『学歴社会は誰のため』(PHP新書)を出版した、組織開発専門家の勅使川原真衣(てしがわら・まい)さんにお話を伺いました。
学歴を努力や我慢の指標として見る人も
—— まず先に結論をお伺いしたいのですが、「学歴社会」、つまり学歴によって人の価値が評価され、就職が左右される社会というのは、今の時点で存在しているのでしょうか。
勅使川原さん:「ない」とは言えません。一部の企業では学歴不問にしていますが、現状では多くの企業が学歴を見て判断しています。
その上で、さまざまな論者が自身の経験談をベースに「学歴は重要だ」「いや、関係ない」と意見をぶつけ合っているのが、現在地となります。いわゆるポジショントークに学歴論がなっていると言えます。
—— 今後変わっていく兆しはあるのですか?
勅使川原さん:難しい質問ですね。たしかに、学歴を気にすることを「ダサい」とする流れは出てきてはいて、大企業の一部が「脱・学歴主義」に舵を切っている例も見られます。ただ、中小企業からは「余裕があるからできるんでしょう」と見られている面もあったりと、そう単純化できない議論です。
—— そもそも学歴を問うというのは、人のどんな面を評価しているのでしょうか。単純に、「頭の良さ」を見ているのですか?
勅使川原さん:「学力」はもとより「努力できるかどうか」「我慢できるかどうか」の代理指標です。勉強を頑張ったかどうか、イヤなことでも我慢してやってきたかどうかや、結果を出すタフさや運の強さがあるかまでも、学歴によって見ている経営者は少なくありません。
しかし、このような人たちは世に言う「結果(成果)」を序列づけて「すごい」「たいしたことない」といった評価をやすやすと下しますが、「学校が苦手だけれど高校まで行った」とか「不登校だったけれどこんなことを頑張った」といったプロセスの努力は評価しません。
努力とひと口に言ってもさまざまな形があるはずですが、「偏差値の高い大学に行ったからすごい」「給料の高い仕事に就いていてすごい」といった、一元的な成果のみを評価する傾向が依然としてあり、それが学歴社会を形作っていると言えます。
—— そうなると、やはり「大学は出たほうがいい」「できれば難関大学、有名な大学のほうがいい」となりますよね。
勅使川原さん:そう思う人が多いでしょうね。ただ、私はこのままでいいとは思っていません。学歴重視型の国家公務員や有名財閥系企業に入れば生涯安泰、ということでもありません。激しい競争にさらされ続けて、道半ばでドロップアウトやバーンアウトする人も多くいる中で、いい学校・いい会社・いい人生をいつまで信じますか。
現実には、「不登校経験があります」「通信制高校卒業です」となると、先に挙げたような学歴を気にする企業や機関で採用において不利に働く場合があるかもしれません。ですが、一度採用されたらバラ色、と言い切ることもできません。
何より、自分のことを認めてくれない経営者のもとで働いても不幸なだけですよね。学歴以外の面をとらえて、「いてくれて助かるよ」「いつもありがとうね」と言ってくれる場所で働くほうが幸せではないでしょうか。
—— たしかに、学歴の高い人が採用される職場以外にも、選択肢は多様にありますね。
勅使川原さん:結局、社会に出るうえで学歴が重要かどうかという議論は、冒頭で少しお話したように、それぞれが自分のポジションからものを言っているだけなんですよ。今の自分の人生を肯定するための発言を方々からしてしまっているように感じます。大学はオワコンだと言い放つホリエモンこと堀江貴文氏も東京大学を中退してから言っていますし……。
—— 学歴社会は存在していると言っても、学歴が低ければ必ずしも不幸な人生というわけではなく、多様な生き方があるわけですよね。学歴に関する議論に振り回されて、多様な選択肢が目に入らなくなることは避けたいですね。

学歴という曖昧な評価が企業の成長を止めている
—— 「学歴がないとマズい」と不安になる気持ちは、子ども自身よりも親のほうが強いかもしれません。実際、わが子を難関大学に入れるために必死に頑張る保護者も多くいます。そうした大人たちが、学歴社会を強固なものにしてしまっている側面もありませんか?
勅使川原さん:ありますね。そうした大人たちの中には、学歴で企業に採用される以外の道が想像できなかったり、そうでない人がどう生きているか見て見ぬ振りをしたりしている人も多いと思います。
私が組織開発者としてさまざまな組織に分け入るなかで気づかされたのは、仕事は人の凸凹を組み合わせて動いているということです。学歴が高い人がいれば業績が上がるわけではありません。優秀な人が優秀な組織をつくっているという幻想から抜け出さずして、日本企業の成長はないのではないでしょうか。組織も社会も、多様な人による多元的な分業で回っています。
—— 「学歴の高い人が社会で活躍するので、学歴を競っていきましょう」という価値観の経営者ばかりでは、どのみち日本企業の成長は止まってしまうわけですね。
勅使川原さん:努力や我慢強さといった曖昧な評価に過ぎない学歴で競わせることで「優秀な人材を育てよう」としても、日本企業が強くなることはありません。学力競争は、現行のテストで測る「学力」を考えても、創造性を競うことはありません。インプットしたものを効率よく正確にアウトプットする力や、過去の頻出パターンを再現することなどを「正解」と呼ぶ競争ですから。
一元的なものさしによる競争を強いているので、人知を超えた新しいものを生み出す<共創力>にはならないんです。創造はひとりの天才によって生み出されるものではなく、チームワークによって生み出されて世に出てきます。新しいものを世に生み出すには、競争で緊張関係を強いるのではなく、チームメンバーが「他者の意見を否定しないで認め合う」と共創を目指していくことも、地味なようで大切なんです。
—— 学歴競争において勝者となったとしても、企業を成長させる力を持てるわけではないのですね。すると、多様な選択肢にも目が向きそうです。
勅使川原さん:社会を支えている仕事は、本当に多様にあります。製造業など、業種によっては大卒よりも高卒人材を求める企業も多いですし、高専卒も人気です。とはいえ、「高卒だと安く雇えるから」と考えている経営者がいるのも事実です。そんな扱いでは長く信頼関係を育めないでしょう。
これからは能力主義をベースとしたメンバーシップ型雇用※・人材マネジメント一辺倒ではなく、入社後の貢献をしかと評価できるよう、ジョブ(職務要件)を整えていくなどの進化が求められるでしょう。採用される側が、「ジョブも不明瞭ならば入社しません」と言えるくらいになるといいなぁと願っています。
—— 学歴にとらわれたままでは、個人にとっても企業にとっても、あまりよいことはなさそうですね。
勅使川原さん:一度競争に勝つと勝ち続けねばなりません。そうではない人は、他人と比べ続けずに自己を最大化させるための選択肢を持っていると言えます。
※メンバーシップ型雇用:職務や勤務地などを限定せずに雇用契約を結ぶ雇用システム
自分の“凸凹”が武器になる:多様な社会で生きるヒント
—— では、現在、自分の選択した進路が将来不利になるのではないかと考えている中・高生は、どうしたらよいのでしょうか?
勅使川原さん:大人たちはいろいろなことを言いますが、長い人生の中で自分の助けになるのは、「周りの人には苦でも自分にとってはあまり苦ではないこと」です。私の場合、小学生のころから毎日エッセイを書いては学校の先生に見せていました。
大学を選ぶときには「文学部はお金にならないからやめろ」などと言われていましたが、結局は今、本を書くことも仕事になっています。これも他の人よりも文章を書くことが苦ではない、寝食を忘れて夢中になれるからできることです。
長い人生の中で、「人に何と言われようと、没頭する何か」は、どこかであなたの助けになるはずです。それを大切にして、より稀有(けう)なレベルへと磨き続けることが大切だと思います。
—— それが音楽でもアートでも、勉強でもいいわけですよね。
勅使川原さん:はい。「好きなこと」というと勉強以外のことと考えがちですが、もちろん勉強でもいいと思います。勉強といっても、学校の授業で習うことに限らず、ギターを弾きたい人は音楽を勉強するでしょうし、YouTubeやゲームの中でも、さまざまなことを学ぶことができます。
AIが発達してきても、現状はAIの答えがすべて正しいとも限りませんので、真偽を見極めるためにも勉強して知識を持つことは大切です。でも、それは必ずしも学校の授業でしか学べないわけではありません。好きなことや没頭してしまうことを入り口に、いくらでも学びは広がっていくはずです。
—— 好きなことを我慢して、その我慢した力を評価されるよりも、好きなことを勉強したことも評価されてしかるべきですね。
勅使川原さん:我慢大会では未来は見えませんよね。繰り返しになりますが、社会の中では、勉強も何でもできる万能選手が必ずしもいい働きをしているとは限りません。器用貧乏がゆえに苦労する人もいます。
組織の力は関わる人の凸凹を組み合わせることで発揮されますから、いろいろな凸凹がないと、噛み合わないんです。自分にできること、苦手なことを把握して、他の人に伝えられることも大切だと思います。組織をうまく回すには、それぞれの状況に応じて働く環境を整える〝合理的環境調整〟が万人に不可欠です。
苦手なことを苦手と言えること、どんな条件下でならマシな成果を出せそうかなど、自分でしっかり知っておきたいところ。周りの評価に合わせて本当の自分を見失っている人からしたら、そうではない人の自己理解や自己探求の力は実はものすごい才能です。
—— たしかに、好きなことと苦手なことがはっきりしていれば、社会の中での自分の活かし方や役割がわかりやすくなりますね。
勅使川原さん:不登校も発達障害も、ユニークネスに他なりません。王道を狙ってレッドオーシャンともいえる熾烈な学歴競争に突っ込んでいかずにすむとも言えます。
他人の評価軸に振り回されず、自分を生きることを、多少のリスクを負いながらも果敢に見つめてきた人たちだからこそできることが絶対にある。たくさんの葛藤を経験してきた・していることに自信を持ってほしいです。
—— ありがとうございました。
取材協力
勅使川原真衣さん
組織開発専門家。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。外資系コンサルティングファーム勤務を経て、組織開発を専門とする「おのみず株式会社」を設立。企業をはじめ病院、学校などの組織開発を支援。近著に『働くということ』(集英社新書)、『学歴社会は誰のため』(PHP新書)などがある。2025年11月に『「働く」を問い直す』(日経BP)、『人生の「成功」について誰も語ってこなかったこと』(KADOKAWA)を刊行予定。
<取材・文/大西桃子>
この記事を書いたのは

ライター、編集者。出版社3社の勤務を経て2012年フリーに。月刊誌、夕刊紙、単行本などの編集・執筆を行う。本業の傍ら、低所得世帯の中学生を対象にした無料塾を2014年より運営。