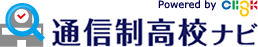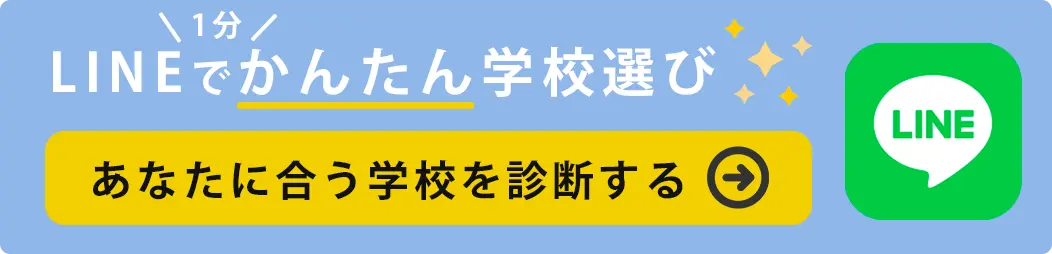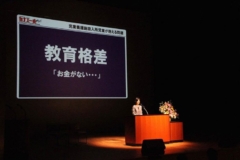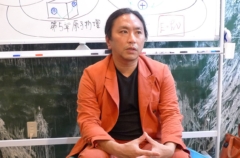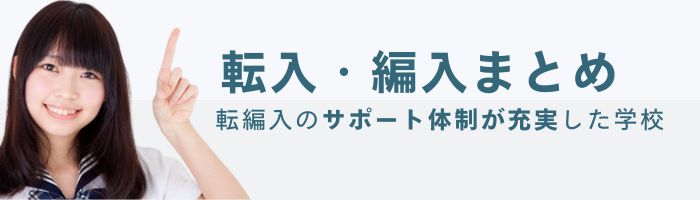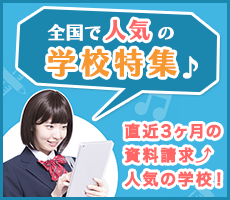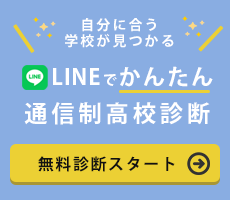夏休みが終わると、多くの中学3年生は本格的に高校進学の準備が始まります。夏休みの間に塾の夏期講習を受けたり、高校の学校見学や説明会に参加したりする生徒も多く、周囲と比べて進路がはっきり決まっていない生徒は不安になるかもしれませんが、まだ大丈夫です。
筆者は10年以上中学生の学習支援活動に携わり、多くの受験生たちをサポートしてきました。同じ中学3年生でも、夏に志望校を絞り込む生徒もいれば、選択肢を広げるために秋まで情報収集をする人、決めていた志望校を秋や冬になって変更する人など、さまざまな生徒がいます。
志望校を決めるペースも、視野の広げ方も、モチベーションが上がり始める時期も、それぞれに個性があるものです。
ここから受験までの半年、どのように進路を決めて、準備を進めていけばいいのかわからない生徒もいるかと思いますが、焦らずに自分のペースで決めていけるよう、今回はアドバイスをお届けします。
秋は学校に足を運んでイメージしながら、比較検討していこう
夏休み期間となる7月、8月には、公立・私立問わず多くの高校が学校見学会や説明会、オープンキャンパス、部活体験会などを開催していました。いくつか気になる高校を見て回っていれば、それぞれの学校を比べて自分に合いそうな進路を考えるヒントになったかと思います。 ただ、どこにも行けなかったという人も心配する必要はありません。
学校見学会や説明会などは9月、10月にも引き続き多くの高校で開催され、加えてほとんどの学校では文化祭も見学できます。
この時期には、気になる学校があればいくつか足を運んでみて、いいなと思うポイントをたくさん探してみてください。
地域によっては、公立や私立高校の合同説明会も秋に開催されていますので、一度にたくさんの学校の先生の話を聞いたり資料を集めたりしたい場合にはオススメです。
「気になる学校」は、現在の自分の学力に見合うところに限らなくても大丈夫です。なぜなら、この後の数カ月の頑張り次第で学力がグンと伸びる生徒も多いからです。行きたいと思う学校ができてモチベーションが上がることで、勉強に集中することができ、学力が大幅に伸びていく生徒も筆者は多く見てきました。
周囲の大人は「できるだけ偏差値の高い学校を」「大学進学実績がよい学校を」などと言うかもしれませんが、高校に通うのは自分自身です。3年間、充実した毎日が過ごせそうな学校、安心して通えそうな学校、自分に合う雰囲気の学校を探してみましょう。
次のようなポイントで探してみるのも、よいと思います。
希望する部活動の雰囲気がどうか
大会で優勝を目指せるような部活がいいのか、結果よりも楽しく仲間と打ち込める雰囲気がいいのか。筆者の教え子の中には、秋の学校見学の際に「自分で写真部を作ってもいいですか」と校長先生に尋ね、実際に入学して写真部を創設した生徒もいました。このとき「いいですよ」と言われたことで、受験へのモチベーションが高まっていました。
校舎のキレイさや、制服のかわいさ
古いトイレや薄暗い廊下などが苦手な生徒もいます。3年間気持ちよく過ごすには、施設面も重要です。制服も同じで、毎日着たいと思える制服のほうがモチベーションは上がります。選択肢が多くて迷っている生徒は、カリキュラムや学力レベルだけではなく、こうした好みから絞り込むのもアリです。
自分が打ち込めそうな科目があるか
中学校と同じ英語や国語、数学などの主要科目だけでなく、プログラミングや料理、イラスト、園芸、機械工作など、さまざまな専門科目が学べる高校があります。はじめはピンと来なくても、学校見学に行くことで具体的に何を学べるのかイメージできて、「自分もやってみたい」と進路を決めていく生徒もいます。
授業や通学のペースが自分に合っているか
中学校では授業についていくのが難しかったり、毎日通えなかったりした生徒は、通信制高校や定時制高校といった選択肢もあります。通信制高校の中には、平日の朝から毎日通学できる高校や、週に1日、3日など選べる高校もあります。全日制高校でも、不登校や発達障害などの生徒が多く通い、中学の勉強から丁寧に復習できる学校があります。高校は中学校よりも選択肢が大きく広がり、個性に合わせた選択をすることができるのです。
地域によっては自宅から通える範囲に高校が少なく、学力ごとに進学先を選ぶのが一般的になっていることもあります。自分が納得できる進学先が選べればいいのですが、「どこもピンと来ない」と感じる生徒もいるかもしれません。そうした生徒は、広域の通信制高校や、住んでいる都道府県の枠を超えて高校を選択し、高校3年間をその地域で過ごす国内進学プログラム「地域みらい留学」を検討してみてもよいかもしれません。
(地域みらい留学:https://c-mirai.jp/)
いずれにしても、10月までは、自分が高校生活にどんなことを求めているのか、どんなことを学びたいのか、どんな雰囲気の学校が合いそうか、自分自身と向き合いながらいろいろな学校を見てもらいたいと思います。
情報収集はインターネットで調べるだけではなく、ぜひ実際に足を運んでみてください。ネットを見るだけではわからない、感じられないことがたくさんあるはずですし、自分がその場にいるイメージもわきやすくなります。
さまざまな高校を見ていく中で、「自分はここに心が動かされる」というポイントがわかってくると、自分自身を理解する手助けにもなっていきます。

受験までの半年、勉強はどう進めればいい?
11月、12月になると、秋までにいろいろ比較検討した学校の中から、志望校を絞り込んでいく時期に入ります。もちろん、もっと早くに決めている生徒もいますが、このタイミングで絞り込んでもまだ間に合います。
ただ、この時期には、実際に受験に合格できる学力が身についているかどうかも含めて、現実的に進路を考えていくことになります。
学習面の準備に関しては、基本的には次のように進めていけば安心です。
9月、10月まで
1〜2年生までに習った範囲で、よく理解できていなかったところや、忘れてしまったところを復習しましょう。
大手進学塾などが開催している模擬試験を夏から1〜2カ月に1度のペースで受けていくと、自分の現在の学力や、どの高校が現実的な選択肢になっていくかがわかるので、おすすめです。
11月、12月
特に公立高校では、中学校の内申点(通知表の評価)が重視される傾向にあります。9月から12月までの学校のテストは、内申点を大きく左右することがありますので、しっかり対策しましょう。
志望校の基準に対して内申点が足りていない場合は、中学校の各科目の先生に「どうしたら内申点が上がりますか?」と質問すると、目安の点数などを教えてくれることもあります。先生にもよりますが、どんどん相談してみてください。
この時期から、志望校や都道府県ごとの入試問題の過去問題集に手をつけ始めるとよいでしょう。授業でまだ習っていない単元も含まれていますが、国語と英語は夏から手をつけてもある程度点数を取りやすいので、早めに取り組んでも大丈夫です。
1月、2月
いよいよ受験シーズンです。過去問題集を何度も解き直して準備してください。
1月の模擬試験で高い合格確率が出ていれば安心ですが、安心できる判定になっていなくても、残り数週間で伸びる生徒もいます。判定によってはこの時点で、より合格しやすい学校に志望校を切り替えるか、最後まで粘るか、選択することになります。
その他、作文や小論文が受験科目に含まれる場合もあります。その場合は、なるべく早いうちに、自分の考えを文章でまとめる練習をしたり、志望理由を練り込んだり、作文のネタに使えそうな自分ならではのエピソードをまとめておいたりすることをオススメします。
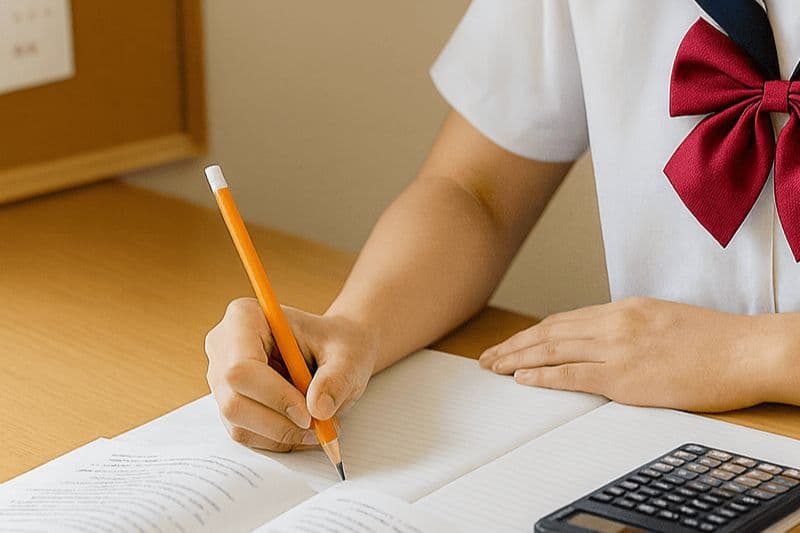
9月からの半年間は、中学校でも丁寧に進路指導をしてもらえるはずですので、志望校に対して自分の学力が見合っているか、内申点は足りているかなど、不安なことがあれば先生に相談しましょう。入試までの手続きについても、中学校の先生がサポートしてくれます。
ただ、「絶対に合格できるところを強く勧める」など、チャレンジすることに対して少し消極的な先生もいます。「先生の言うことが絶対」と思わずに、自分の考えや希望を大切にしてください。
筆者の生徒でも、学校の先生に「受かるはずがない」と反対されてしまった高校に、どうしても合格したいと最後まで粘り強く勉強して、1月の模擬試験で合格確率80%以上の判定をとり、入試本番でも実力を出して合格できた生徒がいます。
ちなみに、夏までに模擬試験を受けて、思ったような点数がとれず、合格確率の判定もよくなかったことで落ち込んでいる人もいるかもしれません。
でも、安心してください。
暑い時期の模擬試験は、自分のスタート地点を知るためのものです。今の結果を見て「この学校は受からないから諦めよう」と考える必要はありません。ここから集中して勉強して、冬までに模試での偏差値が10以上上がるケースも、まったく珍しくはありません。
志望校は、願書を提出する期日まで、変更することが可能です。第2志望、第3志望をあらかじめ決めておいて、1月に変更する生徒もいますので、まったく焦る必要はありません。
今は、周りと比べたり、自分の学力に一喜一憂したりするよりも、来年からの3年間をどう過ごしたいかを考えて、わくわくするようなイメージを膨らませながら勉強に取り組んでもらえればと思います!
保護者にとっても時代の変化を知るチャンス!
保護者のみなさんにはまず、お子さんの高校受験を機に、令和の進路選択の幅広さを感じてみていただきたいと思います。
ご自身の高校進学のときには、「全日制の普通科か、工業・商業科」「学力によって学校を決める」という選択肢しかなかった人も多いのではないかと思います。
しかし、現在はもっと多様な専門科目を学べますし、大学進学率の高い専門科の高校もあります。
通信制高校も現在は全国に200校以上あり、学校に毎日通うのが難しい生徒や、全日制の普通科高校では学べない科目を学びたい生徒の受け皿になっています。
10年、20年前にはなかった選択肢が広がっており、自分たちの時代の「当たり前」とは大きく異なります。この変化を楽しんで眺めてみていただければと思います。
また、お子さんの高校進学に向けて、なるべく早めに費用面のご確認をお願いします。
「授業料が高いので私立高校は無理」と思っていても、現在は高等学校等就学支援金制度によって私立も授業料は実質無償化されており、2025年度からは所得制限も撤廃されてすべての家庭が対象となっています。
ただ、私立高校の場合は、入学金や施設設備費、修学旅行の積立金などが高額な場合もあります。学校によりますが、入学以降どれくらい費用がかかるのかは、早めに確かめて準備をしておいてください。
学校によっては、入学試験の点数によって費用負担が減免されたり、所得に応じて奨学金を受け取れたりすることもあります。
それぞれの自治体や学校によってどのような支援制度があるかも、早めに確かめておくと安心です。
以前、お子さんが通信制高校を選択した保護者の方はこんなことを言っていました。
「自分の時代とはまったく違っていることに驚きました。先に高校生になったお姉ちゃんにももっと広く選択肢を見せてあげられればよかったと思っています。最初は授業料の面で通信制高校は難しいと思い込んでいましたが、支援制度を活用すれば通わせられることにも安心しました」
何より、自分に合った選択肢を自分で見つけたことで、ポジティブに勉強に向かい始めたことがうれしい、とお子さんの成長を喜んでいました。
高校受験は中学生にとって、自分がどのように物事を考えるのか、自分はどんなことが好きなのか、自分が頑張れるのはどんな環境なのか……と、自分自身を見つめて成長していくチャンスです。受験の結果がすべてではなく、この過程が生徒の糧になるはずですので、周囲の大人たちは温かく見守っていけるといいですね。
<文/大西桃子>
この記事を書いたのは

ライター、編集者。出版社3社の勤務を経て2012年フリーに。月刊誌、夕刊紙、単行本などの編集・執筆を行う。本業の傍ら、低所得世帯の中学生を対象にした無料塾を2014年より運営。