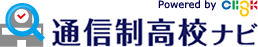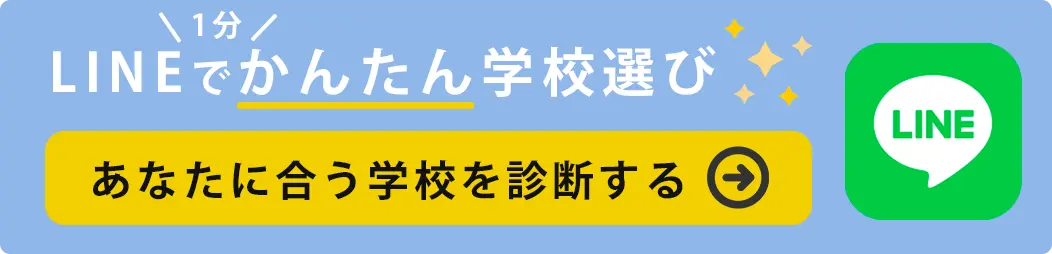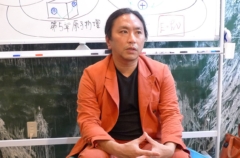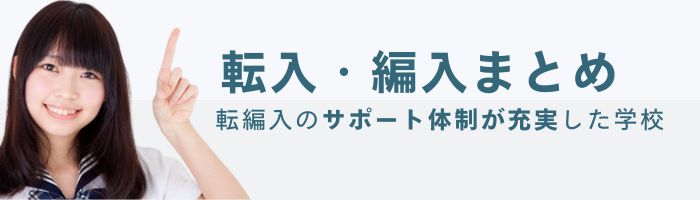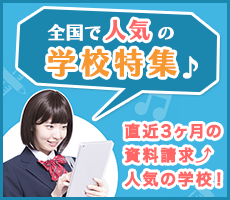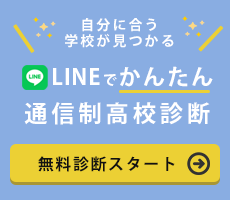多くの学校で新学期が始まる9月1日は、国の調査によると日本の18歳以下の自殺者数が最も多くなる日です。また文部科学省の調査でも、不登校の児童・生徒が休みがちになった時期は9月が最も多くなっています。
夏休み明けの9月は、友達との距離感や部活や勉強へのプレッシャー、生活リズムの崩れなどさまざまな要因から、登校に不安を感じる生徒が少なくありません。
登校してみたものの、人間関係や勉強に不安を感じるようになったり、居場所がないような感覚に陥ったりしている生徒も多いのではないでしょうか。
しかし、子どもの居場所は、学校や家庭だけではありません。学校での居心地が悪く、家にもいづらい、そんな生徒は安心できる別の場所を探してみてもいいかもしれません。
学校以外にも安心して過ごせる“第三の居場所”とは
子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、親として一番心配なのは「じゃあどこで過ごせばいいの?」ということではないでしょうか。
そんな時に頼れるのが、学校や家庭以外の居場所を紹介している「#学校ムリでもここあるよキャンペーン」です。
全国で子どもの居場所づくりを行なっている有志の方々で構成されており、学校や家庭以外にも安心できる居場所や相談場所があることを特設サイトで紹介する形で、2019年から子どもたちや社会にメッセージを送り続けています。
特設サイトは毎年夏休みが終わる時期に合わせて開設されますが、2025年は約50の団体が子どもの居場所・相談場所として登録し、サイト上で紹介されています。
どのような団体・施設が登録しているのか、実行委員会事務局の高橋利道さんに聞いてみると、「フリースクールやオルタナティブスクール、プレイパーク、児童館が多いです。サイトに登録するにあたり、子どもの安心・安全を守るための研修を受けていただいています。研修では子どもの権利を理解し、性被害やハラスメントなどが起こらないように、セーフガーディングを学んでいただきます。また、無料で利用できること、かけこみの利用でも可能なことなどが条件となっています」とのこと。
中には、近年全国的に増えている子ども食堂や、困りごとや不安をLINEで相談できる団体もあると言います。
キャンペーンを始めた背景には、やはり「夏休み明けの子どもの自殺や不登校などの社会課題がある」と高橋さん。
「年々子どもの自殺が増えている中で、子どもだけでなく社会全体にメッセージを届けることができればと思い、このキャンペーンを始めました。昨今は、不登校や自殺、格差など、子どもたちの“育ち”の問題は社会課題として認識され始めています。子どもたちの居場所として機能するような子ども食堂も増えていますし、テレビで特集番組も組まれるようになってきています。ただ、子どもたちが安心して過ごせる居場所はまだ足りておらず、子どもを取り巻く環境がなかなか変わっていない現状もあります。その状況を変えられるのは大人たちですから、大人に向けてもメッセージが届けばと考えています」
では、子どもが安心・安全に過ごせる居場所とは、どのような場所なのでしょうか。
「ジャッジされない場所、ありのままでいられる場所、自分がやりたいことをやりたいようにできる場所だと思います。場所によって“ここではこれができる”と目的が決まっていて、それを目当てに来る子どももいますが、うまくいかなかったりだらだら過ごしたりしても叱られなかったり、自分の存在を認めてもらえる場所であることが重要です」
同じく実行委員会事務局の中村尊さんも、こう話します。
「私は長崎県でフリースクールを運営していますが、子どもたちは『十分に休めたから、やりたいことが見つかった』と話してくれることがあります。学校や家の他に、心身をゆっくり休められる場所が子どもたちに必要だと感じています」
こうした場所はまだ少なく、今後増えていくとよいですが、現状でも、もしかしたら近くに安心できる居場所があるかもしれません。最近は図書館でも、「学校に行けなくてもここにおいで」とメッセージを発信しているところが増えてきています。
今、学校や家で過ごす時間に苦しさや不安を抱えている生徒は、動けるようなら、第三の居場所を探してみてもよいのではないでしょうか。
最後に、お二人に生徒たちへのメッセージをいただきました。
「学校に行って心身ともにボロボロになること、人の目を気にしすぎて疲れきったり、自分を押し殺して苦しみ続けたりすることは、果たして将来の自分のためになるのでしょうか? 学校以外の居場所を選んだ子どもたちの中にも、数年後には幸せになっている人が多くいます。“レールから外れたらダメ”“負け組になる”という思い込みを取り払い、視野を広げてみてほしいです。何が自分に合った道なのか、立ち止まって考えてみても大丈夫です。“学校じゃなくても何とかなった”人はたくさんいます」(中村さん)
「大人たちは、“夢を持つことが素晴らしいこと”と、子どもたちに夢や目標に向かって行動することを期待しがちです。でも、そんな大人たちの中にも高校生ぐらいの頃にやりたいことがなかった人は、たくさんいたと思います。それでも大人になって働いて日々を過ごしています。“学校に行かないなら何かを見つけなきゃ”ではなく、日常を過ごす中で少し外に出て、自分が楽しいと思うことを見つけてもらえたらいいなと思います。その余裕がなければ、ゆっくり休んでからで大丈夫です。まずは生きることを大切にしてください」(高橋さん)
学校がダメならどこか別のところで、必ず何かを見つけなければいけないというわけではありません。ただ自分にとっての居場所として心を休められる場所、楽しいと感じられる場所が見つかるとよいですね。

https://www.youtube.com/watch?v=r86W-o46FVM
子ども自身が伝える「不登校でも大丈夫」というメッセージ
現代では、リアルな場所ではなく、インターネット上に自分の居場所を見つけたり、インターネット上で表現することで社会とつながっていたりする生徒も多くいます。
2023年から毎年夏に行われている「不登校生動画甲子園」は、ショートムービープラットフォーム「TikTok」を活用し、テーマに沿った1分以内※のショート動画を制作するコンテストで、不登校を経験した13歳以上20歳未満の個人またはグループを対象に作品を募っています。2025年も多くの作品が集まり、8月24日に表彰式が行われました。
※1分以内となったのは2025年から
大会の発起人で審査委員も務める石井しこうさんは、当コンテストを夏休み期間に開催することについて、こう話します。
「夏休み明け前後は、不登校や子どもの自殺が多くなる時期です。この時期に必要なのは“等身大のメッセージ”なのだと思います。毎年、動画甲子園に送られる作品に込められたメッセージは、大まかに言えば“不登校でも道はあるんだ”ということ。学校へ行けないことで人生が終わるわけではないことを訴える作品が多く集まっています」
2025年は「不登校で見つけたこと」をテーマに、昨年のおよそ2倍を超える400本以上の応募がありました。応募作品の中に込められたメッセージについて、石井さんは次のように話してくれました。
「絵を描くことや音楽活動、あるいはアニメやゲームといった“好きなこと”を見つけられたという内容が多くありました。居場所や仲間を見つけたという人、感謝することの大切さを知ったという人もいました。私が感心したのは、“不登校で見つけたのは自分だった”というメッセージです。見つけたことはたくさんあるけれど、それらに共通しているのは“自分で見つけたこと”である、と。すなわち、不登校で見つけたことは“自分”だったんだ、と結論づけた内容でした。不登校は“学校へ行けない”という面ばかりが注目されますが、子ども自身は不登校を通して学ぶこと、得ることが多いのだと改めて感じましたね」
こうした動画のメッセージを受け取り、勇気づけられたり、安心感をもらえたりする生徒も多いのではないでしょうか。
今年は、昨年の大会終了後から1年かけて構想を温めてきた人や、この大会を目標に準備してきた人、フリースクールの仲間たちとひとつの動画を作り上げたグループなども参加しており、じっくり作り込まれた動画も多かったそうです。こうした表現の場もまた、学校以外の居場所になっていると言えそうです。
石井さんからも、この時期の生徒たちに向けてメッセージをいただきました。
「新学期を迎えた生徒さんの中には、苦しい思いを抱えている人もいると思います。ぜひ同じように苦しかった人の思いに耳を傾けて、自分を大切にしてもらえたらうれしいです」
不登校生動画甲子園の受賞作などは、TikTokの公式noteから見ることができるので、気になる人はチェックしてみてください。
https://note.com/tiktok/n/nf9f1b92289cb
新学期の9月は、子どもにとっても親にとっても不安が大きくなる時期です。大切なのは「学校に行けない=終わり」ではなく、「学校以外にも安心できる場所やつながりがある」と知っておくこと。
今回紹介した取り組みや子どもたちの声が、親御さんが子どもを支えるヒントになれば幸いです。
<取材・文/大西桃子>
この記事を書いたのは

ライター、編集者。出版社3社の勤務を経て2012年フリーに。月刊誌、夕刊紙、単行本などの編集・執筆を行う。本業の傍ら、低所得世帯の中学生を対象にした無料塾を2014年より運営。