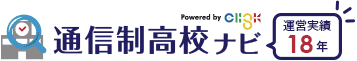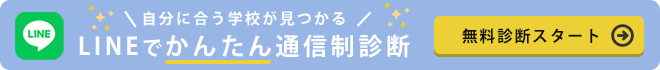不登校をきっかけに家族ぐるみで離島へ移住! 隠岐・島前で、初めて「目標」と出会えた高校生
先輩に聞く
2016/09/05

島根県の沖合60キロに浮かぶ4つの島。隠岐諸島だ。
島々は、大きく2つのエリアに分かれ、島後(どうご)・島前(どうぜん)と呼ばれる。島後は最も大きな島ひとつを指し、空港もある隠岐の玄関口だ。ビルが立ち並ぶ街並みや商店街もあり、広々とした野山も広がる。
残る島3つを合わせたエリアが島前だ。島後とは異なり、離島らしいこぢんまりとした雰囲気が漂う。島前の島のひとつ、中ノ島(隠岐郡海士町)には、島前で唯一の高校「隠岐島前高校」がある。

隠岐島前高校は、3学年180人ほどが学ぶ学校だ。ここでは、島が高校を支え、高校が島の将来を担う人材を育てようという「島前高校魅力化プロジェクト」に取り組んでいる。
プロジェクトが始まったきっかけは、生徒の減少で迎えた廃校の危機だ。過疎化による人口の減少に少子化が拍車をかけた。1クラスの維持がやっとで、通学範囲内の島前3島から中学生を集めても高校の維持には絶対数が足りず、将来は、もっと厳しい環境に陥る予想もあった。
そこで、高校は自らの改革に努めた。魅力化プロジェクトをスタートし、特色あるカリキュラムでの魅力的な授業を行い、生徒自身が自ら考え、学び、学んだことを実践していける環境を地元の協力を得ながら構築した。
島と高校は、島内出身者のみならず本土出身の「離島留学生」も受け入れている。家族ぐるみで島へ移住する一家もいれば、学校が用意した生徒寮のほか島民宅への下宿制度もあり、家族と離れ子ども1人で高校生活を送ることもできる環境だ。進学希望者には、3島が共同で運営する公立の学習塾がサポートする仕組みまで作った。

今回、話を聞かせてくれた佐本沙智さんは、島前高校の3年生。中学時代の不登校をきっかけに、家族ぐるみで島へIターン移住してきた。
神戸生まれ・神戸育ちの佐本さん。プロジェクトが軌道に乗りつつあった4年前・中学3年生のときに、母親と弟の家族3人で島へ移り住んだ。
父親はいない。佐本さんは「一度も会ったことがない」と言う。仕事を持つ母親のもとで育った。弟の父親にあたる男性は一時、母親と結婚していたことから、血はつながらないものの家族4人で暮らした経験はある。とはいえ母親と男性の結婚生活は短く、仕事に忙しい母親の代わりに小学生のころから家事一般をこなし、弟の面倒を見てきた。
「母親の代わりに弟の面倒を見ることに一生懸命だった時期は、居場所がないと感じたことはない」と佐本さん。母親とは感情的にぶつかることが多かったものの、近所で暮らす祖母の支えもあって、学校に通い部活の吹奏楽にも打ち込んでいた。
しかし、思春期に差しかかると佐本さんは、次第に家を空けるようになった。母親は看護師で、勤務の都合上、夜間の不在が重なる。中学生になって交友関係も広がり、屋外で夜を過ごすようになる。コンビニや古本屋など、深夜でも店内や店頭が明るい場所はいくらでもあった。
母親はそんな佐本さんに迫り、何度も厳しく問いただしたという。もともとぶつかることが多かった2人だから、いさかいはエスカレートした。何ら結論を見いだせないまま時間は流れ、1人で過ごす時間が多くなっていった。

学校に通えなくなったきっかけは「たいしたことではなかったと思う」と佐本さんは振り返る。張り詰めていた糸がプツンと切れたかのような気持ちだったという。ずるずると不登校を重ね、自宅の2階にこもった。
佐本さんを心配した母親は、「神戸を離れよう」と決断を下した。環境を変えることでの佐本さんの立ち直りに期待をかけたのだ。移住の候補地はいくつかあったが、候補地それぞれが力を注ぐ取り組みのうち、環境や条件の魅力から隠岐諸島を選んだ。
中学2年生の夏休み、島へ家族ぐるみで移り住んだ。弟は移住を嫌がったというが、居場所をなくしていた佐本さんは、どこへ行っても同じだという気持ちで本土を離れる船に乗った。島には診療所がある。そこで、母親は看護師として勤め始めた。
島の中学校は、小規模だ。転入生の佐本さんは目立つ存在だったが、思ったよりもすんなりと周囲に溶け込めたという。奇異の目を感じたことはない。移住を嫌がっていた弟も、島の暮らしになじんだ。
「高校には進学しなくてもいい」。そう考えていた佐本さんだったが、周囲に引きずられるような形で、島前高校へ進学。1学年2クラスの高校は、生徒同士の関係性が密接なら、教員との距離も近い。グループとして取り組む必要がある授業課題も多く、佐本さんは自然に、さまざまな人・さまざまな考えに触れる機会を持つことができた。
島前高校の授業は、地元の人々と共に取り組むカリキュラムもある。地元には、古くからの島人もいれば、佐本さん家族のようにIターンを志して本土から渡ってきた人も人口の1割以上いる。校外でも、よりさまざまな考えに触れる中で明るさを取り戻す一方、自らの考えを持ち、その考えを「私はこう考える」と明確に打ち出せる高校生に成長した。
大学への進学も決めた。進路が決まれば島を出ることになる。大学を卒業後、島へ戻るか、本土へとどまるか。そこまでの進路は「まだ、はっきりとは……」(佐本さん)とはにかむ様子を見せたが、神戸時代には「なかった」はずの将来が、島に来て一気に開けたようだ。
最近では、母親との関係も穏やかになった。買い物などを一緒に楽しむこともある。
「母は、長年に渡って神戸で積み重ねた看護師のキャリアを捨ててでも、私のために島へ移り住む道を選んだんだなと思う。島では、キャリアを再び一から積み重ねてやる直すことになるのに……」
家族の絆も、島に渡って取り戻すことができたようだ。

「どこから来たの?」
見知らぬ人を見かけた島人は、気さくに話しかけてくることが多い。しかし「何しに来たの?」「なんで来たの?」とは誰も聞かない。住み慣れた土地を離れて島へ渡るには、それなりの「つまづき」があってのことだと、島ぐるみで心得ているかのようだ。
家族ぐるみの移住にせよ、子ども1人での離島留学にせよ、この島に渡れば「つまづき」を意識することなく、新しい人生のスタートを切ることができるかもしれない。
ここ隠岐は、都から追放された人々の流刑地としての歴史がある。島前の海は、波が荒い日本海では珍しく穏やかな湾を作り、沖を行き交う船の避難港でもあった。傷ついた人・疲れた人を迎え入れるだけの素地があるのだろう。
(前田 昌宏+ノオト)
※本記事はWebメディア「クリスクぷらす」(2016年9月5日)に掲載されたものです。