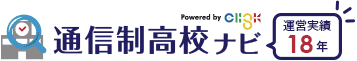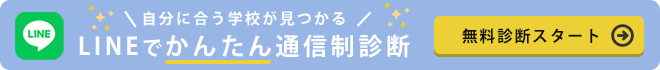他者の悩みへの想像力を持つ1つのきっかけにーー『吃音―伝えられないもどかしさ』著者・近藤雄生さんが中高生に伝えたいこと
専門家に聞く
2020/01/18

コミュニケーションで言葉に詰まったり、同じ音を繰り返したりすることで、思うように話せなくなる吃音(きつおん)。言葉によって相手に理解を求めるのが難しく、状況や問題を理解してもらうのも容易ではないため、当事者は“二重”のコミュニケーションの難しさをかかえています。
そんな吃音と向き合ったのが、ノンフィクション作品『吃音―伝えられないもどかしさ』(新潮社)です。著者である近藤雄生さん自身も、吃音に悩んできた当事者。
5年もの歳月をかけ、当事者や家族、研究者、言語聴覚士、自助グループなど、吃音を取り巻くさまざまな方へ、ノンフィクションライターとして取材を行ってきました。
近藤さん自身が吃音に悩んだ高校生時代にも焦点を当てつつ、いま、「吃音」とさまざまな形でかかわる中高生に伝えたいことを伺います。
吃音に関わる80人以上への取材をもとに描いたノンフィクション
――『吃音―伝えられないもどかしさ』を書くにいたったきっかけを教えてください。

吃音は、僕自身にとって切実なテーマです。2002~2003年に吃音に関する1本のルポルタージュを書いて以来、いつかこのテーマにじっくりと取り組みたいと思っていました。
そう思いつつ、海外を旅しながらライターとして文章を書くことを始めていったのですが、旅をしていた最中、29歳を少し過ぎたころ、僕の吃音に変化が起きました。最初は浮き沈みがありながらも吃音の症状が軽減し、さらに5年ほど経ったころには「吃音がなくなったかもしれない」と思えるまでになりました。
自分が吃音で悩んでいるときは、他の当事者に会って取材をすることにどこか怖さがありました。けれど、症状が軽減し、吃音とある程度の距離が置けるようになったとき、「吃音とようやく向き合える」と思ったんです。そうして2013年に吃音の取材に着手できました。
もし僕自身が吃音に悩んでいるままだったら、きっと吃音の当事者に会い、その人生を書くことはできなかったと思います。
――出版後、どのような感想が寄せられましたか?
当事者とそうでない方、両方から多くの感想をいただきました。特に出版直後は当事者ではない方からの感想のほうが多かったです。「そういえば、小学校の同級生がそうだったのでは」「知らずにからかったりしていたかもしれない」「この本を読むまで意識したことはなかったけれど、吃音がこんなに苦しいものだとは……」などですね。
当事者ではない方に吃音の苦しさを知ってほしいと思っていたので、コメントを多くいただけたことが本当にうれしかったです。思っていた以上に世間の人は吃音の問題を真剣に受け止めてくれるように感じました。
その一方で、当事者の方からは、「吃音者たちのリアルな苦悩が詰め込まれているから、読み進めるのが苦しい」という声も届きました。それは辛いところでした。
どもらないように、神経をすり減らした高校時代
――著書の中に、近藤さん自身の吃音の兆候は小学校時代に始まった、とありました。当時をふり返り、何かきっかけなど思い当たることがあれば教えてください。
特にこれといったきっかけはないんです。いつもより喉に力が入る、言葉がつかえるという感覚はあったものの、小学校・中学校時代に「どもる」ことはほとんどありませんでした。
たとえば、中学校のころは生徒会長を務めていて、全校生徒の前で発言する機会も多かったのですが、吃音に悩んだ記憶も特にないんです。
――深刻な症状が出始めたのはいつごろのことですか?
高校生のころからです。喉のあたりが動かなくなって何も言えなくなったことがありました。それ以降、突然言葉が出なくなる場合があることに自覚的になりました。
僕の場合、言い換えのできない言葉を言おうとすると、詰まってしまう。自分の名前の近藤を言うときも、「こ、こ……」みたいに。
ただ、すらすらと言えない場合も「いや」や「あの」を挟んで、言えるタイミングを待てば、なんとか伝えられたので、周囲がすぐに吃音だと気づく状況ではありませんでした。だから、僕が吃音で悩んでいたことを、当時の友人や両親を含め、ほとんど誰も知らなかったと思います。
――高校時代はどのように吃音と向き合われたのでしょうか。
どもって声が出ないまま口だけがぱくぱくしたりするのを、恥ずかしいと思っていたので、何とか隠そうと必死でした。毎日が切実で、神経をすり減らしながら過ごしていたように思います。
たとえば、友人と一緒にカラオケに行くとき。大きな音が流れている場所などでは特に話しづらくなってしまうため、カラオケルームに入って「近藤、ウーロン茶を注文して」なんて友達から言われたらどうしよう、電話口でどもってしまって注文できないかもしれない、といった不安がよぎります。そのため、いつも何気なく、電話から一番離れた場所に座るようにしていました。
また、バスケットボール部のキャプテンを務めていたのですが、練習の途中などの円陣が怖かったことも覚えています。円陣を組んで「いち、に、さん」と声を出すのがキャプテンの役割。「どもって言えなかったらどうしよう」と不安でたまらなかったです。
幸い、副キャプテンが何でも話せる親友のような存在だったので、彼にだけ吃音のことを打ち明け、「どもりそうになったらひざを叩くから代わりに言ってほしい」と頼みました。
実際にどのくらい彼のひざを叩いたか記憶があいまいですが、あまり叩かずに済んだんじゃないかな。彼が隣にいてくれる安心感も大きかったのだと思います。
――現在、ノンフィクションライターとして活動されていますが、昔から書く仕事を目指していたのでしょうか。子どもの頃の夢や進路を教えてください。
僕は数学や物理が好きで、夢は物理学者になることでした。物理学者を志す自分に本はいらないと思っていたので、高校卒業までに読んだ本は累計でも10冊に満たないくらいだったんじゃないでしょうか。
だから、大学に入った当初も、理系のことだけを学んで物理学者になろう、という気持ちでいっぱいでした。ただ、思った以上に物理は難しく、物理学者は諦めることにしました。
そんな僕に次の夢を与えてくれたのが、ある一冊の本でした。それが、『宇宙からの帰還』(中央公論社)。ジャーナリストの立花隆さんが、アポロ計画に参加したアメリカの宇宙飛行士たちにインタビューして書き上げた名著です。
自分の誕生日はアポロ11号の月面着陸の日と同じだと知っていたので、昔から宇宙にも興味を持っていました。自分は宇宙に行ったらどんな影響を受けるのだろう。そのことを知りたくなり、宇宙飛行士を目指そうと思いました。ただ、宇宙飛行士になっても緊急時にどもってしまうのでは……という不安もあって。
宇宙分野のエンジニアや研究職として企業に就職したりするコースも考えましたが、吃音があって、電話が苦手だったため、就職するのはやめて、フリーランスで生きていく道はないかと考えるようになりました。
そして、本の面白さを知るうちに、だんだんとサイエンスライターという仕事に興味が湧いてきたんです。そのため、大学院では環境問題を学ぶほうがいいかもしれないという気持ちになり、学ぶ分野を宇宙から海に変えたり、有名科学雑誌の編集部に連絡してみたりしました。
しかし、沢木耕太郎さんの本に触れたり、旅をしたりするうちに、だんだんとサイエンス分野より、ノンフィクションを書きたいと思うようになりました。
「想像力」を大切にしてほしい

――身近な友だちや同級生が吃音であるとわかったとき、どう接したらいいのでしょうか。
必ずこうすればいいという答えはありませんが、一つは相手がどもって言葉が出ずにいるときは、せかさず待ってあげて、安心して話せるような環境をつくること。でも、ただじっと待っているのがいいか、それとも言おうとしている言葉を推測してフォローするのがいいか、正解はありません。
吃音の症状の重さも人によるので、「こう対応すればいい」というマニュアルはないんですよね。大切なのは、とにかく相手の気持ちを理解しようとする姿勢と想像力だと思います。
もしかしたら、考え抜いて取った行動が必ずしも相手の望む対応ではないかもしれません。しかし、そういった行動は相手にとっての安らぎにつながるのではないかと感じています。
――最後に中高生自身とその家族、教育関係者へのメッセージをお願いします。
何かちょっとでも違和感があったり、つらさを感じたりしたら、とりあえず誰かに相談してほしいです。
インターネットによって人と人がつながり、交流が容易になったいま、当事者同士の意見交換はもちろん、ともに行動したりもしやすくなっています。同じ悩みを持つ人と話し、つらさを共有することで、救われることも少なからずあるはずです。
子どもの吃音と向き合う家族や学校の先生は、まずは吃音について勉強して知識を持って、周りがからかうことなどないよううまく促したりしてもらえたらと思います。話の聞き方を工夫して、子どもの気持ちに寄り添い、ちゃんと見守っていることが伝わるような雰囲気を作る。そうすれば子どもたちも相談しやすくなると思います。
吃音以外にも、当事者にとってはものすごく大きな悩みだけど、周りからはなかなかわからないことはたくさんあります。『吃音―伝えられないもどかしさ』を通して、吃音への理解を深めるとともに、他者が抱える問題を想像することの大切さを感じてもらえればうれしいです。
(企画・取材・執筆:水本このむ 編集:鬼頭佳代/ノオト)
取材先

近藤雄生さん
東京大学工学部卒業、同大学院修了。2003年、旅をしながら文章を書いて暮らそうと、結婚直後に妻とともに日本を発つ。 オーストラリア、東南アジア、中国、ユーラシア大陸で、約5年半の間、旅・定住を繰り返しながら月刊誌や週刊誌にルポルタージュなどを寄稿。2008年に帰国、以来京都市在住。最新刊に『吃音 伝えられないもどかしさ』(新潮社、講談社本田靖春ノンフィクション賞・新潮ドキュメント賞最終候補、本屋大賞ノンフィクション本大賞ノミネート作)。大谷大学/京都造形芸術大学非常勤講師、理系ライター集団「チーム・パスカル」メンバー。
※本記事はWebメディア「クリスクぷらす」(2020年1月18日)に掲載されたものです。